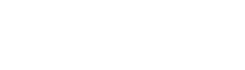作品詳細

電波、異臭、工学の枝
そういうわけで詩は覗きなのだ
問題は詩とはこうだという決定的なことはもはやなく、詩であるかないか、詩は、確率的に存在する。(「確率詩論」より)
言葉で映画を撮る男、藤井晴美。今作では半自伝的な雰囲気を漂わせる詩篇も織り交ぜ、読者をさらなる〈吐き気をもよおすように魅惑的な〉深みへ誘う。
ぼくが小児科医院に程近い住宅地を歩いていると、頭上でヘリコプターの爆音がしきりにするので、見上げると真っ黒い巨大な円盤状のものが二機飛んでいた。するとそれは音もなくぼくのすぐ間近に迫ってきて、小学生の女の子が数人ぼくのそばを駆け抜けて行った。円盤は彼女たちを追っているのだ。ぼくも危ないと思い、走り出した。あぜ道を抜けると左側に小学校の校庭が見えたので、ぼくはそこの体育館に避難しようと思った。体育館ではちょうど、小学生が集合して床に座り教師の話を聞いていた。
ぼくはそこに紛れて窓から迫り来る巨大な円盤をじっくり観察した。アダムスキー型に似た円盤で十個位の円筒形のものが下部の内側に沿ってついており、それらは青緑から白に発光し、よく見るとものすごい勢いでそれぞれが回転し、まるで呼吸でもしているかのように伸び縮みしながら出たり入ったりしていた。ぼくはこれが殺人場エンジンというものかと思い、ショックを受けた。精神病院で目が覚めたように。
その後、ぼくはぼくのたずねた小児科医の紹介状を持って、格子縞の雨の降っている暗い路地をあっちからこっちへとちょろちょろとうろついた。同じところを何回も歩いて、皮膚科のある医院を見つけた。中に入るとだれもいなかった。患者もいない。ぼくはすぐに診察を受けることができた。黴が服のように体中にはびこっているのだった。と言っても服は黴だらけ。医師はそう言うと別の部屋に行ってしまった。すると一人の看護師がやってきて、ぼくの体を青い蠟のような冷たい紫外線で焼いてくれた。その時、皮膚がちぢれて焦げているような異様な匂いがしていた。が、それは本当に新鮮な奇妙な、胸を押し広げるような真空の肺の匂いだった。薄暗い部屋ではその看護師とぼくの二人きりだった。それが済むと、今度は看護師はぼくの体に生クリームを塗ってくれた。看護師の手は重たそうでゆっくりしていた。白い看護師が、ぼくの背中を滑り、ぼくの胸を押さえた。ほとんど口をきかず、看護師の手はさらさらと撫でた。ぼくを愛していても決して間違っていない手だった。看護師のウエハースのように覆いつくす甘味があるだけだ。世界には、ハウスダストクリーム混入の長い時が過ぎた! 裸のぼくは恥ずかしかった。相手を殺すくらい突き刺す。そうすると子供が生まれる。ぼくはじっとして医師の机の上の解剖写真を見ていた。すると、空飛ぶ円盤が飛んできた。ぼくは一週間ほどそこの医院に通ったが、ああ虫が鳴いている。ざっと胎盤∧ザーッ、ザーッと。たまりかねて力いっぱい! だから物音も立てず何もしなかったばかりか校庭の日射の中で苦しくすがるように、だがいらいらしながら首を絞めてやると思いながら無口に臆病に笑いながらぼくはあなたを好きです! と今日も時計の心臓を抱いて眠った。だが、ぼくは眠りながら、眠ったまま体だけは眠ったまま、心だけが不意に起きだす。ぼくは体を覚まそうと一日中辞書ばかり引いている。ついにいやなバッテンを見る。ダメ、ダメ、ダメ、ダメ。全く滑稽な話さ。中学校の校庭に案山子のように不時着したんだから。まるで納屋みたいな湿ったところであの二人は彫像のようにぎこちない夫婦のようだった。すると、ビスケットの空飛ぶ円盤が飛んできた。ぼくは一週間ほどそこの医院に通ったが、いつも二人きりのあ
と父が言った。……
私の首筋は、石のごろごろした埃っぽい道を銅鑼の鳴る壁の方へ放射している。
私の首筋はメッキした盲腸で鶏冠と同棲してみようか?
(「クチクラ層の殺人」)
詩集
2018/01/18発行
四六判
並製